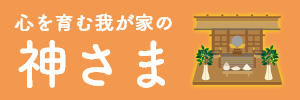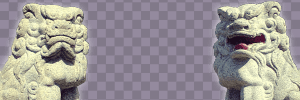-
多太神社

- 御祭神
-
衝桙等乎而留比古命 仁徳天皇 応仁天皇 神功皇后 比咩大神 軻遇突智神 蛭児命 大山咋命 素盞嗚命 継体天皇 水上大神
- 鎮座地
-
小松市上本折町72
- 氏子区域
- 小松市旭町飴屋町扇町上本折町幸町白嶺町清六町大文字町白山町福乃宮町三日市町光谷町大和町八幡町
- 由緒
当社は創祀が遠く古代までさかのぼる古社である。社縁起によると、6世紀初め、武烈天皇の5年に男大跡(オオトノ)王子(後の継体天皇)の勧請によると伝えられ平安時代初期には延喜式内社に列している。寛弘5年(1008)に舟津松ケ中原にあった八幡宮を合祀し、多太八幡宮と称した。寿永2年(1183)源平合戦のとき、木曽義仲が本社に詣で斉藤実盛の兜鎧の大袖等を奉納し戦勝を祈願した。室町時代初めの応永21年(1414)には時衆第14世大空上人が実盛の兜を供養された以来歴代の遊行上人が代々参詣されるしきたりが今も尚続いている。大正元年に本殿後方から発掘された8千5百余枚に及ぶ古銭は、室町中期の15世紀初めに埋納されたもので、当時の本社の活動と勢力の大きさを示すものである。慶長5年(1600)小松城主丹羽長重が古曽部入善を召出され三男の右京に社家を守らせ、舟津村領にて5丁8反243歩を寄進されたことが記録にある、加賀三代藩主前田利常は寛永17年(1640)に社地を寄進し慶安2年(1649)の制札には能美郡全体の総社に制定し能美郡惣中として神社の保護と修理にあたるべきことを決めている。元禄2年(1689)松尾芭蕉が奥の細道の途次本社に詣で実盛の兜によせて感慨の句を捧げている、歴代の加賀藩主及び爲政者はいたく本社を崇敬し神領や数々の社宝を奉納になった。明治15年に県社に指定された。歴代の宮司はその人を得、よく精励し神社の守りにあたってきた、由緒と歴史を持ち、広く人々の尊信を受けてきた本社の神威はいよいよ輝きを加えている。
- 宮司
-
上田 秀一 (莵橋神社 宮司)
- TEL
- FAX
0761-24-2315
本務神社
兼務神社
-

八幡神社
能美市坪野町ハ62
-

冨樫八幡神社
能美市金剛寺町巳75
-

八幡社
白山市西佐良町リ22
-

諏訪神社
白山市瀬木野町ヌ160
-

三輪神社
白山市数瀬町イ81
-

白山神社
白山市上吉谷町イ116
-

八幡神社
白山市若原町ハ28甲
-

三上神社
白山市三坂町ト50
-

八幡社
白山市三ツ屋野町ロ230
-

大和社
白山市三ツ瀬町ハ7
-

武健社
白山市左礫町ハ223
-

志津原神社
白山市広瀬町ニ191
-

白山神社
白山市釜清水町ホ99
-

白山神社
白山市河合町ニ64
-

八幡神社
白山市河原山町ニ155ヘ65
-

八幡神社
白山市下野町ロ190-2
-

八幡社
白山市下吉谷町ロ30甲
-

八幡社
白山市阿手町カ70
-

日吉神社
小松市蓮代寺町ハ丙120
-

諏訪神社
小松市矢崎町イ61
-

木場少彦名神社
小松市木場町イ209
-

八幡神社
小松市本江町247
-

北浅井神社
小松市北浅井町ろ9
-

符津白山神社
小松市符津町ヨ15甲
-

八坂神社
小松市不動島町乙174
-

白山神社
小松市白山田町ホ24
-

八幡神社
小松市波佐羅町ハ141
-

磯前神社
小松市波佐谷町カ302
-

日用神社
小松市日用町卯27
-

八幡神社
小松市南浅井町ハ183
-

菅原神社
小松市長谷町ツ18-3
-

小松琴平神社
小松市地子町1番8
-

白山神社
小松市池城町ハ47
-

諏訪神社
小松市大嶺中町1-393
-

大領神社
小松市大領町そ46、47
-

白山神社
小松市打木町ヲ6
-

千木野神社
小松市千木野町ヘ103
-

八幡神社
小松市千代町ル584甲
-

少彦名神社
小松市千代町ホ572
-

熊野神社
小松市西俣町ヘ207甲
-

白山神社
小松市赤瀬町丙155
-

八幡神社
小松市西荒谷町ニ125丁
-

八幡神社
小松市西原町ト21
-

磯前神社
小松市瀬領町ク19甲
-

新保神社
小松市新保町ヘ107
-

白山神社
小松市上り江町ホ158乙
-

小野神社
小松市小野町巳191
-

白山神社
小松市松岡町ヲ40、41
-

八幡神社
小松市小山田町ヘ67甲
-

白山神社
小松市若杉町ワ11
-

三谷白山神社
小松市三谷町イ109
-

今江春日神社
小松市今江町6丁目605
-

八幡神社
小松市江指町イ10
-

向本折白山神社
小松市向本折町己240-2
-

石部神社
小松市古府町カ169
-

八幡神社
小松市金平町ナ15
-

幡生神社
小松市吉竹町ヘ253
-

岩上神社
小松市岩上町ロ158
-

谷郷社
小松市丸山町チ26
-

白山社
小松市観音下町ハ90
-

沖太郎丸神社
小松市沖町ロ138
-

八幡神社
小松市井口町イ61
-

白山神社
小松市粟津町ワ88
-

土室白山神社
能美郡川北町土室ル215
-

田子浦神社
能美郡川北町田子島レ71
-

中島神社
能美郡川北町中島ワ34
-

磐出神社
能美郡川北町山田先出信38
-

磐出神社
能美郡川北町山田先出レ89
-

三反田八幡神社
能美郡川北町三反田ハ128
-

壹ツ箭粟嶋神社
能美郡川北町一ツ屋ヘ15
-